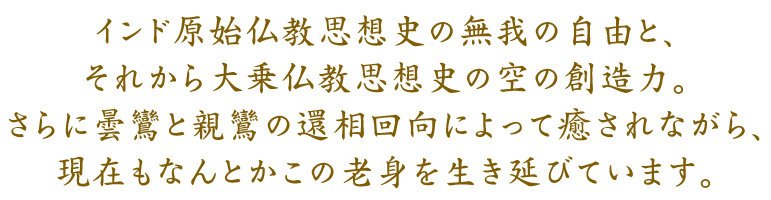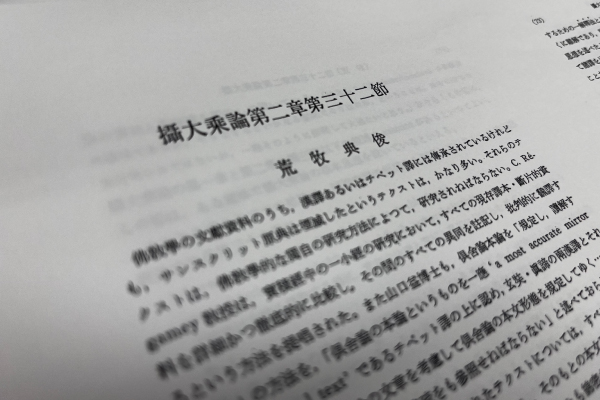01.はじめに
インドの原始仏教の思想史の無我の教えについて申し上げます。無我であるということは、根源的に自由であることです。我があると縛られるけれども、無我であることによって、根源的に自由である。
当面、原始仏教の思想史の無我の自由ということに関連して、私が今まで子どもの頃からというか、中学生や高校生の頃からどうやって仏教の勉強するようになったかを説明させていただきます。私自身、在家の人間でお寺と関係が無い環境で育ってきたものですから、大学に入って仏教を勉強するという道に行くまでに中学の時代に受けた先生の熱烈な教育というのかな、人生教育というのかな、そこから始まって、自分なりに探し求めて、大学に入ったら仏教の勉強しようと思ってきたのです。そういうふうな中学生の頃から高校生の頃にかけて、どんなことを考えて仏教に到達したかというようなことを無我の自由で選んできたのだとお話できればと思います。
はじめに、大乗仏教思想史の根源の言葉として「空」という言葉があります。「空」ということこそが、実は大乗仏教運動、すなわち大乗経典を生み出してきた根本にある「仏教、芸術運動」というのかな。仏塔を中心とする、あるいは、仏塔から仏像が出現してくる、そういう仏塔を中心として芸術を創造し、仏像を創造した。この「空」の創造力によって、それから学びながら、自分の仏教の勉強の創造力というものを身に着けていきたいなということ。
学生の頃はインド仏教の専門家として勉強してきたし、教育を受けてきたし、今お話したような仕方で原始仏教も勉強した、大乗仏教も勉強したように、インドの仏教の歴史事実を確認するという勉強をずっとしてきたのです。アメリカから帰ってきて、就職したのが京都大学の人文科学研究所という中国学のセンターでした。そこで、中国仏教の助手として就職したものですから、ゼロから中国仏教の勉強を始めないといけなくなってしまったのです。それは、普通なら学生の頃から東洋史を勉強したり、あるいは中国文学を勉強したり、中国学のトレーニングをずっと受けて、中国学の助手になっている同僚たちがいっぱいいるわけですけれども、私はインドのことは勉強してきたけれども、中国のことはなんにも勉強してない。そうするとゼロから中国学を始めないといけなくなって。そういうゼロから始めながら、中国の仏教の思想史というものをまた歴史事実として確立するというようなことを勉強してきました。
そこから学びとった曇鸞と親鸞の「還相回向」という言葉によって生かされて、現在もなんとか生き延びています。曇鸞、親鸞の還相回向というお言葉は、実は私も毎日お唱えしながら生きているようなものなのです。還相回向がなかったら毎日の生き方ができなくなるように思います。
私、この歳になると私と同年配、大学時代の同級生の方々が、次々に亡くなってくれるのです。彼らと親しくして、本当によくしてもらったのに、何かお葬式もできないような形で別れてしまっているのがつらくて。そのことを思い出すと、やはり彼らの還相回向によって生かしていただく以外に彼らにお詫びする道は無いなと。毎日そんなことを思いながら、曇鸞大師、親鸞聖人が教えてくださった、還相回向があるのだと。ごく最近、亡くなっていかれた彼らの還相回向によって生かされて生きていく以外に自分の生きていく道は無いなというようなことを思って、毎日生活していますから。
私としては、インド原始仏教思想史の無我の自由と、それから大乗仏教思想史の空の創造力。さらに曇鸞と親鸞の還相回向によって癒されながら、現在もなんとかこの老身を生き延びています。一応、そういう無我と空と還相回向という言葉によって、支えられているのですということを、少しでもご説明できればよいかと考えています。

02.『摂大乗論』研究について
―荒牧先生は長尾雅人先生と『摂大乗論』を研究され、金字塔を打ち立てられたと後学は理解しています。そこで先生が『摂大乗論』から学ばれたことについて、お教えいただけますか。
まず、『摂大乗論』をなぜやったかという話ですね。それは、私がどうして仏教の勉強をするようになったのかということと、無関係ではないでしょう。『摂大乗論』を本格的にやり始めたのは、大学院生になってからです。確か、私は4年生の卒業論文のときには、『唯識三十頌』や『中辺分別論』など。2回生のときにサンスクリット語を習って、そのサンスクリットを使って、テキストを読めるようになるために、いろいろなサンスクリットのテキストを読みました。そういうわけで『大乗荘厳経論』や『中辺分別論』や『唯識三十頌』から入りましたね。
あの頃の京大の文学部の、サンスクリットの教育は、現在から考えても、最高レベルの教育をしてくださったと、私は思います。なぜなら、その頃京大の梵文学というのですけれどもね。梵文学で、サンスクリットを我々に教えてくださったのが、大地原豊という先生で、この先生は「日本(特に京大)のインド哲学や梵文学の研究は、伝統仏教の研究に縛られていて、本物のインド学、仏教学になっていないのだ」と。そうお考えで、御自分はフルブライトの第1回の留学生として、アメリカのペンシルベニア大学でサンスクリットをご研究なさったのです。
大地原先生は、「アメリカとしても、日本の若い人がアメリカへ来て勉強するのだからということで、とても大事にしてくれた」とおっしゃっていました。英語の基礎教育から全部やってくれて、その上でペンシルベニア大学のヴェーダ学の大先生がおられたので、その方のもとで勉強されました。
その当時、世界のインド学の中心はパリでした。パリ大学のソルボンヌに、ルイ・ルヌー先生という方がおられて。大地原先生は、ペンシルベニアで勉強したあと、どうしてもルヌー先生に会いたいということで、先生を訪ねてフランスのソルボンヌに行かれます。
そのとき、ルヌー先生は大地原先生が大変優れた学生であるということを見抜かれて、自分の研究の、とても大切な部分を、「大地原さん、あなたやって」という形で任せられた。ルヌー先生はヨーロッパにおけるヴェーダ学の本当に大学者だった。ヴェーダ学をふまえた上で、サンスクリットという言語を本当に理解するためには、サンスクリット文法学の伝統がインドにあるから、文法学の伝統をふまえて、サンスクリットを研究しないといけないということを認識しておられたので、大地原先生には「お前は文法学をやれ」と。『パーニニ文法』というのですけれどもね。
そして、大地原先生が京大でサンスクリットを教え始めた第1回は、私の先輩で、小林信彦という人です。小林さんはその後、大地原先生の後継者になります。
私はその大地原先生の2年目の学生だったのですね。だから、大学2年生で初級サンスクリットを学ぶときに、本物のサンスクリット学者に初級文法を教えていただいているので、それが私の基礎になっていると思います。
やはり優れた先生に教えていただくということは、例え初級の文法であっても、言葉の根本を教えていただいた。私にとっては、サンスクリットという言語は、今でもものすごく大切な言語で、その言語を本格的に理解することなしには、インド哲学はもちろんですが、仏教学も十分には理解できない。だから、そういう本物のサンスクリットを2年生のときに教えていただいたので、ある程度サンスクリットが読めるようになっているわけです。
それで、3年生ないし4年生で専門課程に進んだとき、今度は大地原先生と関係なく、自分で好きなテーマをやりたいということで、さっき申し上げたように、その当時の仏教学界で話題になっていた、安慧の注釈を伴った『唯識三十頌』を、まずサンスクリットで読みました。だから、私の最初の論文は、『唯識三十頌』にもとづいたもの(「唯識思想における十二支縁起解釈」『印度学仏教学研究』11(1)、1963年)なのです。
―なぜ『摂大乗論』に着目し、研究されたのでしょうか
そのようなことも、その3年生ないし4年生で『唯識三十頌』から入って次々とサンスクリットのテキストを読んでいったことから始まりました。
その頃、そうやって少し本格的に仏教の勉強を始めて、まだ仏教学という全体が、どんなふうになっているのかということを、何もわからないままだったので、自分なりに当時の日本のインド学、仏教学会への状況などを勉強していたのだと思いますが、たぶん東京大学の宇井伯寿先生が『摂大乗論』の研究をしておられたし、宇井伯寿門下の方々も、ずいぶん『摂大乗論』を研究しておられた。今から考えると、宇井先生が、『摂大乗論』を研究なさった必然性が理解できるように思います。私もその後、中国仏教を勉強しましたので中国仏教の中に摂論宗というものが出来上がっていたプロセスも、今、やっとわかるようになりました。その当時は、宇井先生が『摂大乗論』を研究された必然性を、何もわかっていませんでした。
それでも、当時の学界の状況などをふまえて、それから私はもともと仏教が勉強したくて大学に入ってきたのですが、基本的には哲学の勉強がしたかったのです。
それは、フッサールやハイデッガーといったヨーロッパ哲学の最先端をしっかり勉強した上で、その哲学をふまえて、初めて仏教が理解できるようになるということを、知らず知らずのうちに考えていました。当時の京大には西谷啓治先生や、西田幾多郎先生以来の哲学者の方々が仏教を研究しておられた。特に西谷先生は、『摂大乗論』をとても深く理解しておられました。
もちろん、漢訳でやっていらしたのですけれどもね。だから、西田門下の哲学者の西谷啓治という先生が哲学をふまえて仏教を理解するという道を開いておられて、それを学生の時代に、ずっと西谷さんの授業には全部くっついて聞いて回るようなことをしていましたから、学ぶことができたのだと思います。
そういうような目で、その仏教哲学のエッセンスは何だろうと考えて、やはり『摂大乗論』だと考えたのです。それは、当時は原始仏教のことも何も知らないし、大乗経典のことも知らない。
しかし、仏教哲学のエッセンスはどうやら『摂大乗論』だということをマスターコースの学生の頃から考え始めて。それで、『摂大乗論』を勉強しようとしたのですが、いざやってみるとご存じのように、これは難物なのですね。なぜ難物なのかといいますと、サンスクリット原典がないからです。いまだに「ない」のです。もしかしたら、あるかもしれないという期待を持たせてくれた時期もありましたが、いまだに見つかっていないのです。
漢訳が4本とチベット訳があって、原典がないのですね。ところが、訳だけで研究して行こうとすると、ほかの訳と合わないことがたくさんあるのです。
先ほど申し上げた宇井伯寿先生や、その宇井伯寿先生の門下の方々は、「真諦訳の『摂大乗論』が一番優れているのだ」という判断のもとで、真諦訳『摂大乗論』を選んでおられたのですけれども、玄奘訳は、どうやら玄奘のそういう意識の解釈が入っているということで、あまり重要視されていなかった。しかし、必ずしもそういうふうには断定できないですね。私、今この年になって、宇井先生がなぜ真諦訳『摂大乗論』を勉強されたことが、よくわかるようになったと申し上げたが、実は、それは宇井先生の中国仏教の影響を受けた『摂大乗論』研究の結果として、宇井先生は真諦訳『摂大乗論』を研究していらしたわけなのです。
その中国仏教の伝統を受けた『摂大乗論』研究からすれば、真諦訳『摂大乗論』は重要ですが、本当は中国仏教に限定されているのですね。はっきり申し上げると、宇井先生だけではないのです。もう江戸時代以来の日本の仏教学者は、仏教哲学というものを、『大乗起信論』に基づいて理解しているわけです。
明治になって近代仏教学が始まってからも、仏教学者の仏教哲学の理解は、『大乗起信論』の哲学をふまえて、仏教哲学を理解しているのです。それは、宇井先生のような仏教学者だけではなくて、鈴木大拙のような本物の禅の体験をした方でも、『大乗起信論』から入っていらっしゃる。
隋の前に、南北朝という時代があって、その南北朝の中でも東魏北斉と西魏北周に分かれるのですけれども、実は西魏北周の仏教の研究がほとんど行われていなくて。それで私が京大の人文研にいた比較的最後の頃、北朝仏教から隋唐という、そういうテーマで共同研究をやったのです。それは、北朝仏教の中でも西魏北周の曇延という人が『大乗起信論』をつくったのだという、結論になったのです。
だから、『大乗起信論』は、中国仏教のエッセンスだけれども、インド仏教のエッセンスではないのです。そういう『大乗起信論』の成立に関わって、真諦訳『摂大乗論』が重要な役目を果たしているので、『大乗起信論』と真諦訳『摂大乗論』を合わせて研究する摂論宗というものが、隋仏教の主流になっていくのです。
その影響を日本の近代的な仏教学も、全部受け取ります。宇井先生がその中心ですけれどもね。それで、宇井先生は真諦訳の『摂大乗論』ということを、研究していらしたのです。
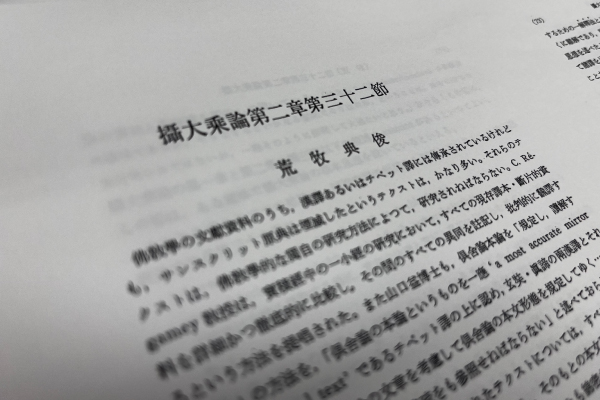
03.小学生から大学生にかけて 恩師の話
―研究の動機として「哲学が勉強したかった」とおっしゃいました。
その前に先生が受けられた中学時代の熱烈な教育というものは、その「哲学を勉強したかった」につながってくるのですか。
小学校の頃から少しずつ、本を読むということが面白くなっていたのだと思います。初めはその地域の小学校に、新制中学が置かれていたのですね。ちょうど私が中学2年生のときに、四日市市が日永村も内部村も河原田村もみんな統合して、四日市という市の中へまとめ上げてしまった。
私が中学2年生のときです。私は日永小学校の出身だから、日永村の南中学なのですけれども。河原田という村で、中学校の教師をしておられた辻信彦先生という方が私の担任になられたのです。
情熱に燃えていた先生でした。もう本気になって、我々中学生に、自分の人生を教えてくださったのです。国語の先生だったのですけれども、教科書もきちんとあるのに、教科書なんて使ったことがないのです。先生は演劇がお好きでね、武者小路実篤の「人間万歳」のような演劇を中学生にやらせるなど。そういうことをしておられた先生だから、本物の演劇には、どういうメッセージがあるのかなどというようなこと。そんな話をして、授業で教科書を使ってしゃべられたことはない。もう自分の人生をぶつけて「昨日、こういうことがあったよ」と言うと、もうそのことで我々にどうやって生きるのが、本当の人間の生き方なのかと。
その後、先生は滋賀県に近江学園という学校に赴任されました。ここは戦後の養護施設の第1号なのです。糸賀一雄という方が近江学園を始められたんですけれども。糸賀先生の知的障害のある子どもたちの教育の理念に、辻先生は非常に感動なさって、中学の教師からそこの近江学園の教師になられたのです。先生なりにずいぶん苦労しながら知的障害のある子どもたちの教育には、どういう教育が必要かということを身をもって実践しておられたのです。
それで、高校生の頃から「人生をいかに生きるべきか」というような問題を焚きつけられたのでしょうね。自分で本を読もうと思って、もう片端から読んでいたように思いますけれども。その頃一番一生懸命に読んだものは、トルストイでしたね。
トルストイが残した人生に関する教訓みたいなもの。私は小説の部分ではなくて、そこの部分が面白くて、図書館に行って、トルストイ全集の最後にあるそういう人生論の書物を、毎日読んでいました。
おそらく、それでキリスト教のことも、老子のことも、孔子のことも、あるいはヨーロッパ哲学のことも、トルストイを通して学んで、「本当に生きるということは、どういうことだろうか」ということを考え始めました。
それから、高校生くらいまで続いているのだけれども、それはいつの間にか、哲学の書物へと私を導いてくれて。高校2年生の頃だったかな。キェルケゴールに関心を持って、キェルケゴールの本を読んでいたし、ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』かな。そんな本も中学、高校1~2年の頃、授業が終わると図書館へこもって、そればかり読んで。それが楽しみでした。
辻先生の影響があって「人生をどういうふうに考えたらいいのか」というようなことを、求めていたのだと思います。それで、いろいろ読んで高校の2年生くらいまでに、キェルケゴールやニーチェなど。
その頃、京都に住むようになったのですが、京都の府立図書館に行って、そういう本を見て、初めてカントという名前を見つけたりしましてね。哲学という分野が、中学校・高等学校の国語の中にはないでしょう
やはり中学生あたりから、哲学を学問として教えるのではなくて、生き方の考え方として、そういう哲学の考え方を学んでおくということが、今の日本の教育に少し欠けている面ではないかと思います。そういう中で、2年生から3年生になる頃、「やはり仏教が一番深そうだ」と気づき始めて、いろいろなことを勉強した。辻先生自身も、仏教にご関心があったということもあると思います。それで高校2年生から3年生になって、受験の準備をする頃は、もう仏教の勉強をしようかなと考えていたので、大学に入ったら、先ほどから申し上げたように、京都大学の西谷啓治先生門下で、辻村公一先生から京大哲学の一番いいものを学びながら、自分は仏教を勉強しようと考えていました。

04.シカゴへの留学から原始仏教経典への問題意識
私は大学院が終わるまでは、その仏教哲学というか、『摂大乗論』の哲学でずっと勉強してきて、仏教と哲学の全体系としては、どんな構造になっているのかを勉強できたと思うのですが、ちょうどドクターコースが終わって、もちろんすぐに就職があるわけではないものですからね。
私はフルブライトの留学生の選考試験を受けたのです。
それは、今まで仏教哲学をやってきたけれども、もう少し視野を広げたい。仏教といってもその前に大乗経典運動があるし、ゴータマ・ブッダ由来の原始仏教という仏教がある。そちらのほうへ広げていきたいなと考えていました。
そしてアメリカのシカゴ大学に、インド哲学の大先生で、ファン・バイトネンという先生がおられましてね、オランダ出身の方なのですけれども。まだ大乗仏教も、原始仏教も勉強しているわけではないのだけれども、その先を見据えて考えたとき、アメリカのシカゴ大学におられるファン・バイトネン先生の学問が、どうやら自分に一番必要な学問であるかもしれない。そういう直感があるのではないかな。ちょうどそのシカゴ大学には、ファン・バイトネン先生だけではなくて、もう1人、宗教学のミルチア・エリアーデという先生がおられて。それでエリアーデ先生の宗教学も、私には面白かったのです。だから、シカゴに行けば、エリアーデ先生の宗教学を習えるし、ファン・バイトネン先生からサンスクリットをふまえた、『マハーバーラタ』という叙事詩なども学べるなと考えました。
フルブライトの奨学金によっては、アメリカの大学はどこへでも行けたのです。ハーバードでもいいし、ペンシルベニアでもいいし、イエールでも、どこでも行けるのだけれども、私はもうシカゴ以外行かない。シカゴにすると決めていて。それで間違っていなかったと思います。
シカゴは大学全体の雰囲気も、非常によかったしね。学生はよく勉強するし。あの頃の学生たちは、みんな本気になって勉強していたね。そこに入れてもらったし、またエリアーデ先生の授業は面白かった。本当に宗教のエッセンスはこれだ。いや、宗教の哲学はこういうものだということを、もう生で教えてくださる。そういう先生だったし。
ファン・バイトネン先生は、私がこれまで『摂大乗論』しかやっていないので、それでは仏教の研究にも不十分だということを、わかってくださったから、真っ先に私にウパニシャッド哲学の手ほどきをしてくださった。インドのヴェーダの宗教の背景をふまえて、ウパニシャッド哲学というものが成立している事も学びました。
ファン・バイトネン先生は、その後ずっと『マハーバーラタ』という叙事詩の全訳を始められて、終わらないうちにお亡くなりになってしまったのです。やはり叙事詩の哲学を、一番深く理解しておられた先生で、ファン・バイトネン先生のところで、叙事詩の哲学を勉強することができました。先生が私に教えてくださった一番大事なことは「パーリ語を勉強しないといけないよ」ということだったと思います。だから、私にパーリ学の手ほどきもしてくださいました。
そういうわけで、インドのヴェーダやウパニシャッドから叙事詩の哲学をふまえて、パーリ語で原始仏教のテキストの研究をするという道筋を見いだすことができました。シカゴ大学にいたのは、たった一年ですが、私にとってはもう本当に、自分がガラッと変わる根本転回の時期だったと思いますね。やはりアメリカ中からトップレベルの学生たちが来ていて、彼らがシカゴで勉強したあと、ハーバードやイエールなど、いろいろなところへ移っていって偉くなっていくのです。
私にとって、ウパニシャッドや叙事詩、パーリで原始仏教を勉強する道が開けてきたので、「やっと、原始仏教から勉強し始めましょう」ということになったのです。そういう立場から日本における従来のパーリ語を中心とした原始仏教研究を見ていると、なんか根本が抜けているように思うのです。
ゴータマ・ブッダが「四聖諦をお説きになりました」「十二支縁起をお説きになりました」ということが、もう基本前提になっていて、そういう教理の説明ばかりが原始仏教の研究になっているのですが、私のようにウパニシャッド哲学の流れをふまえながら、叙事詩の哲学が発達していく。
どうしてそういう状況の中で、ゴータマ・ブッダは、仏陀としての教えをお説きになったかというようなことを考えていくと、何が抜けているのだろうと思いながら、自分でいろいろなパーリ語の原始仏教の仏典を探し回って。そのとき、私、原始仏教の教理を説いている経典というものは、みんな、散文の経典なのです。プローズ、散文で書かれた経典。従来までの原始仏教の研究の中で、ほとんど無視されていたものがそれ以外、前に韻文の経典があるよということでした。
仏教の中には、仏教徒たちが韻文で口承伝承、暗唱して伝えてきた韻文の経典があるということ。それは、ファン・バイトネン先生が直接教えてくれたわけではなく、自分でそう考えたものだと私は思います。
最初に読んだものは、たぶん『ダンマパダ』だと思いますから、『ダンマパダ』のようなテキストを読み、それからまた『スッタニパータ』にも入ってくると、どこかに書いたのですが「ああ、ここには生きた仏教がある」という感じがした。
仏教徒たちの生の声が聞こえるという感じがしました。韻文の経典をずっと読んでいくと、彼らが暗唱して伝えていたから、自分たちの経典なのです。だから、それを読むと面白いのです。
それに対して、散文の経典は「四聖諦はこうです」「十二支縁起はこうです」と、先生が教壇で弟子に教理を教えるときに使う教科書なのです。だから、自分たちの宗教体験が生に出ていないのです。
それに比べると、どうやら韻文経典は面白いということで、韻文経典に関心を持ち始めて勉強していた時期に、講談社が原始仏典というシリーズで、原始仏典の基本経典を、現代語訳するというプロジェクトを提出してきました。
私は、散文の部分には関心がないから、やる気が全然なかったのですが、その中で「スッタニパータを全部訳してくれ」という話がきました。それが今、文庫本にもなっている『スッタニパータ[釈尊のことば]』です。
講談社の原始仏典シリーズを監修しておられたのは、長尾雅人先生でした。先生は、私にとって『スッタニパータ』を訳すことが必要だと考えておられたのだと思います。先生はそういうことは、一切口にしない方でした。
黙っているうちに、究極的に親切なのです。そういう方は、いらっしゃるのではないですか。何もしゃべらないけれども、何もしゃべらない中で、一番親切な人は、そういう方でしたね。そうだ、長尾先生は、仏教伝道協会の理事長をされていた時期がありましたね。そうだ、そうだ。ここにつながっているのですね。感慨深いです。
そんなことで、『スッタニパータ』の全訳をやらせていただいた。そうか、私はあのとき京都大学の人文研にいて、中国仏教の勉強が大変だったから、1人で全部できなくて、自分のできないところを、京大の後輩の榎本文雄さんと本庄良文さん頼んでやってもらったのです。私がやったのは、第1章と第4章ないし第5章で、本庄さんに第2章、榎本さんに第3章でした。
それで、『スッタニパータ』の中でも一番古い「アッタカヴァッカ(八詩頌の章)」というのがあって、その中にゴータマ・ブッダ直々のお言葉は必ずあると。読んだら直々のお言葉だって、聞こえてくるのです。そういうテキストに出会うことができたので、それが生まれ出てくる背景を勉強しようと思ったときに、どうしてもジャイナ教の古いお経もやらないといけないし、そのジャイナ教の背後に、『マハーバーラタ』や『ウパニシャッド』もあるということも、だんだん見えていたのです。
そうですね。アメリカから帰ってきたあと、京大人文研の助手になって、中国仏教の勉強をしないといけない。他方でアメリカから学んできたパーリや、ウパニシャッドなどの勉強も続けたいというので、人文研の助手時代はもう朝から晩まで勉強を続けさせていただきました。
そういうことで、原始仏教を勉強し始めてみると、やはり『スッタニパータ』から始めて、次の段階で韻文経典が成立し、最後に散文の経典が発達していったという筋道は、私なりには見えてきました。
その後、そういう関心を持って研究をしてくださっているのは、本庄良文さんや榎本文雄さんくらいで、今はそれをする人がいなくなってしまいました。
そういう意味では、「若い人には、もう少しパーリの韻文経典を本格的に読んでほしい。そのために私らがした訳は、きっと役に立つよ」と言いたいです。
05.空の思想と創造力
―つづきまして「空」の話にいきたいと思います。「空」という言葉をめぐって、先生は「創造力」とおっしゃいました。
現代、ヨーロッパを中心に地球環境をもっと大切にする方向に、ヨーロッパの科学技術をコントロールしていかないといけない。科学技術は、このまま放置しておくと地球環境をどんどん人間の都合のいいように変革してしまって、地球全体の環境を破壊する方向へ動いているのではないかという声が、ヨーロッパを中心に今起こっているのです。
そうすると科学技術に基づいて、どんどん発達してきたこの資本主義経済は、どこが悪いのかと。資本主義の精神に基づいて、正しい仕方で利益を得て、発展してきているではないかと。どういう歯止めをかけたらいいのかという問題は、科学技術に基づいて発達してきた資本主義の内部には、どうも答えが見えないのです。
そういうとき、地球全体の生命をどういうふうに理解し直して、生命というもの。人間の生命だけではなくて全ての生きとし生けるもの、植物も、動物も全部含めて、地球全体の生命を大切にする、環境を大切にするという方向に向かっていくような哲学がどこにあるか、どこにそういう哲学を求めたらいいのというとき。私は、仏教哲学をもう少し考え直してほしいと言いたいのです。
つまり、仏教こそ地球全体の環境を守るにふさわしい哲学をきちんと準備しているのだから、その仏教哲学というものに基づいて、地球全体の科学技術に歯止めをかけるような哲学として、仏教哲学を読み直していくという時期がそろそろ始まっているのではないでしょうかと言いたいのです。
そのときに一番問題になるのが、空をどう理解するかということなのです。思いつくまましゃべらせていただきますけれども。空というのは、ゼロということなのです。
なぜゼロという教えを説くかといいますと、少し話が飛んでしまうけれども、地球全体に生きている生き物は、皆、身体を持っているのです。どんな小さな虫でも、ミミズでも、植物でも、カビでも。皆、身体を持って生きている。我々も身体があるから生きているので、身体が交通事故で壊されてしまったら生きられないわけです。金澤さんが書いていらしたように、東日本大震災で、大津波で身体が流されてしまえば、何千人何万人という方がお亡くなりになるわけです。身体が機能している限りは、生きていることができるのだけれども、そういう洪水に巻き込まれて息もできなくなってしまうというところで、大勢の方々がお亡くなりになっていくわけです。だから、身体がある限り、生きている物は1つ、2つと数えることができるのです。
ところが、1人1人の身体の中で生きている生命というのは、「本当に数えることができるの?」と言ってみると、大変問題があるわけです。私は、今、こうやってお話をさせていただいていますけれども。皆様が生きていらっしゃるから私は話をできているので、人形さんがそこにおられると話ができないのです。生きていらっしゃる方がおられると思うからということは、私が生きている。皆さんが生きておられるという中ではじめて、コミュニケーションが可能なのです。だから、生きているということは、ひとりひとりが身体をもらって別々に生きているのではないのです。生きている者同士、常にコミュニケーションを持ちながら生きている。それは、我々人間のような動物だけではなくて、植物や虫ですら蚊や虻でも、きちんと血を吸いにくるではないですか。彼らも生きているから、血のにおいがすると飛んでくるではないですか。それもこっちも生きているからです。彼らも死体の血は、吸わない。生きているということは、ひとつひとつばらばらに生きているのではない。そうではなくして、生命そのものは「ゼロ=無限大」としかいいようがないわけです。私は仏教の哲学で空という教えを説くのは、一つ二つと数えてはいけない。数えるところに分別(ふんべつ)が働いている、分別を捨てきってしまいなさいという意味で、龍樹菩薩は空だとお説きになった。
仏教は生命というのは細胞のような、ばらばらな存在ではなく、生命と生命は、つねにコミュニケートをしながら身体を持って生きていると考えます。
そういうことですから、私は空というのを0次元の生命そのものというか、あるいは英語でいうときは、The zero-dimension of the existential communal essence of life as suchと定義します。つまり、生命そのものというものに基づいて。Existential communalという言葉を使っているものだから、人間だけみたいだけれども。人間ひとりひとりの実存は、ばらばらな実存ではなくて、ほかの実存とコミュニケートしているコミュナルな実存だと。実存というと、虻や蚊などの虫けらは、実存という言葉を使わないのですけれども。生きているという点を考えれば、彼らもExistential communalに生きている。私はそういう理解の仕方を地球全体のこの生命というのを、Life as such、生命そのものと理解して、生命そのものの上にいろいろな我々、人間ももちろん含めてですけれども、Existential communalなエッセンスを持って生きている。それを身体がある限り数えるけれども、数えるレベルで見るのではない。なぜなら、そこには分別が働いて数えているからです。分別を捨てなさいというときに、zero-dimension、数えられる面で生命を見てはいけないというのが、龍樹菩薩の言おうとした空性の教えだと理解できないかなという方向に考えようとしています。
龍樹菩薩から大乗仏教哲学は始まるわけですが、大乗仏教哲学が始まっていく原動力に、大乗経典運動があります。大乗経典運動は、実は仏塔を中心とする仏教芸術。特に仏像の芸術を中心とした仏教芸術の発達の中で、大乗経典がある重要な役目を果たしていると考えます。
―創造力の発露 仏教美術の発展に関して
インドの仏教芸術の発達史の中で、いつどこで仏像が出現したかというのは、古典的な大問題です。仏教美術そのものは、仏像以前からインド各地で発達していて。インド全土、いろいろなところに仏像以前の仏教芸術というものが実在しています。何年前になるだろう。私、長年インドに行ったことはなかったのですが、カナガナハリという新発見の遺跡があって、そこから大量の仏教美術が出土しました。仏塔に張りつけてあった石板のパネルに絵が描いてあるのです。仏塔に60枚張りつけてあった。そういうものが、長年の間に埋もれてしまって。小山のようになって隠れていたので、全然気づかれないままカナガナハリというところに小山として存続していたのです。
ところがカナガナハリは、ちょうどクリシュナ河という大きな河の本流の脇にあるのですけれども。河の水を利用して、水力発電をしよう。あるいは、インドは乾燥がひどいので、河の水を塞き止めて、灌漑用にして農業もできるようにしよう。そういうクリシュナ河という南インドの巨大な河を塞き止めて、水力発電、あるいは灌漑用の大きなダムをつくるというプロジェクトが始まって。あそこに山がある、これを塞き止めて貯水湖にしてしまったら。島になるかもしれないけれども。ともかくここにこのようなものがあると発掘したら、そこから仏塔が出てきたのです。それが正確には1970~80年ぐらいの事だったと思います。その段階で、今まで誰も知らなかった仏塔とパネルが60個、ほぼ完全に出てきたので大発見だったのですね。
しかもそれが仏像出現以前の仏塔。この次には仏像が出現するという直前段階の無仏像の遺跡がそのままごそっと出てきたというニュースを聞いて。どうしても見たいと思ったので、文科省の科学研究費を申請して、大乗仏教を理解するためには仏教美術が必要だ。そのためには今回発掘されたここをぜひ見る必要があるのだというようなことを書いて、科研費をいただきました。
そのときのメンバーたちと、カナガナハリを見に行くことができて。仏像出現以前の直前段階の実物を見ることができて、遺跡の研究は他のプロジェクトメンバーに任せて。私自身は、自分の立場から仏教思想史の全体像を見渡すということにしたのです。そんなことで、仏教美術がどのような文化運動であるのかというのを直接経験することができて。
私としては、マトゥラーで『般若経』の運動が始まったと。『般若経』の運動は、即座にガンダーラにも伝わるし、南インドにも伝わる。だけど、どうやらガンダーラはガンダーラ独自の大乗経典をつくっていくようです。おそらくガンダーラでは、『阿閦仏国経』や『大阿弥陀経』。浄土教の根本になるような経典がつくられる。それ以外に『大集経』という経典のグループがあって。これは、教理的には非常に重要なのですが、そういうものがおそらくタキシラという仏教遺跡でつくられる。マトゥラーは『般若経』。南インドにアマラバティという巨大な仏塔の遺跡があるのです。おそらくここは『華厳経』をつくった場所だろうと。
そういうふうに大乗経典運動というのは『般若経』から始まっているのだけれども、いつでもどこでも同じようなものをつくったのではなくて。ガンダーラではガンダーラ独自の仏像と同時に、ガンダーラ独自の大乗経典をつくっている。それから、タキシラもガンダーラの一部ということもできるかもしれないけれども、そこも独自の大乗経典をつくっている。南インドではおそらく『華厳経』がつくられただろう。
そうしたら『法華経』はどこなの?という問題が出てきて。その問題に私は、答えは出せないし、出すだけの勉強の時間はなさそうなので『法華経』の問題は括弧に入れておきたいのですけれども。私としては、それこそ若い人にぜひ確認してもらいたい。ひょっとすると、西インドの石窟寺院を丹念に研究したら『法華経』の源流が見つかるかもしれない。ぜひ、それはやってもらいたいテーマです。ある程度可能性は見ているのですけれども、もう自分では研究できない。だけど『法華経』もそういう意味では、西インドという独自の仏教美術史の伝統があり、石窟寺院の伝統の中で『法華経』が成立した可能性を誰かに証明していただきたいと思います。『法華経』は東インドで作られたといわれているのですけれど、私にはあり得ないと思われます。
東西貿易の繁栄にしたがって、大乗経典運動が起こり広がっていくから、大乗経典運動が中国に入ってきたときは、もうみんな大乗経典を持って入ってくるわけです。
もちろん、小乗の伝統も入ってくるのですが、大乗経典がメインになってくるわけです。そういうような絹の道の貿易の繁栄ということが背後にあって、大乗経典運動は一挙にインド全土に広がるし、中国にまで伝えられる。
東西貿易のついでに、今思い出したのですが、大乗のことをマハーヤーナというでしょう。本来、マハーヤーナというものは、大型の帆船のことなのです。大きな乗り物というものは、キャラバンの馬に比べたら大きいでしょう。それで、大型の帆船のことを大きな乗り物、マハーヤーナと呼んでいました。
大型の帆船のような、全ての衆生を乗せて救ってくれる大乗の教えというもので『般若経』を含む大乗経典運動がマハーヤーナ運動になるので、本来マハーヤーナという言葉は、大型の帆船を意味していたと思いますね。
あのようにすごい力で、あらゆる衆生を運んでくれるものが、大乗の教えだと。そのような意味の転換が行われたので、大乗というものは、大型の帆船だから乗り物なのです。大乗の教えが乗り物なのかということは、なかなか説明が難しいところですよね。だけれども、おそらくそういう背景があって、大型の帆船のような仕方で、一切衆生を運んでくれる。それが大乗だと呼ばれていたのです。
06.後学に向けて
―関連して「波羅蜜」の言葉の漢字の語源も気になります。
「波羅蜜」という言葉を文献学的に基礎づけるためには、言葉が説き始められた『マハーヴァストゥ』という文献に即して研究しなくてはなりません。これは大乗直前の段階。まだ大乗になっていないけれども、次の段階から大乗経典が生まれてくる直前段階の文献です。
その文献が非常に貴重な大乗直前段階のいろいろな伝承を全部取り入れて残してくれている、その大切な文献のテキストを幸いなことに、フランスのスナールという方が、1800年代に出してくださっています。
基本的にはサンスクリットなのですが、完成されたサンスクリットではなくて、当時のマトゥラーの人たちが、日常に使っていた俗語あるいは、口語の文献なのです。その『マハーヴァストゥ』は、『般若経』をこれからつくり上げていく人たちが、直前段階で伝えていた讃仏文学の、本当に貴重な生の資料なのです。それを徹底的に読み抜いて、その中でパーラミターという言葉が、どういう意味で使われているかを洗い直さないといけないのですが、まだそれが行われていない。これも今後やっていただかないといけない分野。
そもそも、『マハーヴァストゥ』は重要な文献だということを、日本のすぐれた方々はみんなご存知で、杉本卓州先生や平川彰先生など、みんな読んでいらっしゃるのですが、私に言わせればまだ読みが浅い。
私はパラマ(最高)、パラマター(最勝な菩薩のあり方)が、パーラミターになっていることが『マハーヴァストゥ』において論証できると思っているのですが、自分でやっていないのです。私としては当面、パラマター(最勝なあり方)という語からパーラミター(最勝であるから自由自在なる菩薩行を行う人)という語がつくられたと理解して、パーラミターを「自由自在な菩薩行」と和訳することにしております。
私が、若い人にやっていただきたいことは、『マハーヴァストゥ』はとても重要な文献だから、もう一度腰を据えて、徹底的にバラバラにして、どういう素材がどういうふうに編集されているかを解明しながら、もう一度研究し直していただきたいと思います。もう私は、それをする時間がないでしょう。若い人にやってもらうしかないですね。
インタビュー日:2022年6月24日
公益財団法人仏教伝道協会 理事室(港区)
文責:金澤豊(仏教伝道協会)